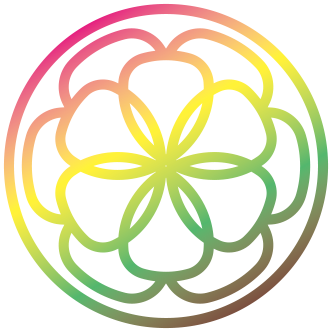子どもたちの想いを尊重する保育に賛同 転職を経て、やりがいや幸せを感じる毎日
異業種から転職した女性お二人が語る“本音トーク”
PROFILE

伊藤礼子さん
副園長 モンテッソーリ0-3教師
看護師として病院やデイサービス等での職場経験を経て、2020年入社。2022年には0~3歳のモンテッソーリ教師の資格を取得して保育に関わるほか、看護師として体調不良のお子さんのお世話にもあたっている。2024年には副園長となり、職員への対応、会社が運営する3施設(保育園2、小学校1)との連携なども担っている。園が安全に運営できるよう、さまざまな立場で幅広く活躍している。

大瀬朝楓さん
モンテッソーリ6-12教師
大学卒業後アドバイザーとして転職エージェントで働いた後、子どもの教育に関わりたいと2022年に入社。資格取得のため1年間の海外留学を経て、6~12歳のモンテッソーリ教師となる。現在は、2024年4月開校のモンテッソーリ教育を主軸とした小学校(フリースクール)の立ち上げ準備、運営を担う。また小学生向けの地域に根ざしたイベント、モンテッソーリ教育を伝えるセミナーなども実施。
前職ではどんな仕事に就き、どんな経緯で転職されましたか?

伊藤:保育の仕事とはかなり違いますね。
大瀬:そうなんです。ただ教育や人のキャリアには興味があり、大学生の頃からコーチングの勉強もしていました。でも学校の先生にはなりたくなくて・・・。
伊藤:えー。どうしてですか?
大瀬:父親が教育者だったので(笑)。それでも教育には興味があり、大学では教育開発や、多様性を尊重する教育のあり方について研究していました。新卒で自分の進路を決める時には、日本社会や「働く」に対する意識が変わっていくことが教育の変化にもつながるのではないかと考え、人材業界に入社しました。
伊藤:そこから、どうして幼児や小学生の教育に興味をもったんですか。
大瀬:多くの人が「自分のありたい姿」を思い描くことが難しいという違和感です。自分の価値観をつくりあげているものって幼少期の家庭環境や学校での生活が多く占めていると思うんですけど、大人になればなるほどその価値観から抜け出すのは難しいですし、家族や社会が引いたレールの上を生きていると、自分がどうありたいかを考えられる機会が失われているなと感じて。それで、今の会社の代表である大谷に連絡して、九州まで行きモンテッソーリ教育の保育現場を見学させてもらいました。その際に、今後小学校もつくりたいという話を聞きました。義務教育である小学校を0からつくりたいと思い、1年で転職を決意しました。
伊藤:初めてモンテッソーリの保育を見たとき、どう感じましたか?
大瀬:衝撃でした! 異年齢で生活する教室の中で、子どもたちが兄弟のように共に生活し助け合っている環境は、社会に根づいていると感じました。そんな子どもたちの姿を大人が信頼しているから、子どもたちの活動はとても自立しているように見えました。
伊藤:人間とはこう生きるもの、というのを子どもたちが環境から学びとっているんですよね。子どもたちは大人がやっていることに興味があるんです。そして赤ちゃん、幼稚園、小学校では興味関心が違うため、年代によるモンテッソーリの特別な資格があります。
大瀬:そうですね。小学校をつくるためにはモンテッソーリの国際免許が必要だったため、2022年4月に入社して、6~12歳のモンテッソーリ教師の資格を取りにいかないかと提案されて。2022年8月末には代表と一緒にオランダで勉強することになったんです。

大瀬:そうですね。0からモンテッソーリについて英語で学ぶ必要があったので勉強漬けの毎日でしたが、とても奥が深く、学びのパラダイムシフトされていく感覚がとても楽しかったです。
伊藤:モンテッソーリの資格をとった人は、みんなそう言うんですよね。苦しかったけど楽しかったって!
大瀬:はい。オランダで勉強しながら小学校の立ち上げ準備も進めていましたが毎日ワクワクの連続でした!
伊藤:本当によく頑張りましたね!仲間ができてうれしい!
大瀬:同じ転職組ですもんね。
伊藤:はい。私は前職が看護師で、病院やデイサービスで働いていました。その後、他の病院へ移り、回復期リハビリ病棟に勤め始めたとき、妹である現在の会社の代表がモンテッソーリの幼稚園を立ち上げました。その影響で私もモンテッソーリ教育の本を読むようになって、その知識を回復期リハビリ病棟で試してみたんです。
大瀬:えっ!やってみたんですか?
伊藤:うん。患者さん本人がやりたいことを満足できるまで、とことんつきあってみたんですよ。そうしたら、みるみる回復して、会話ができなかった患者さんから最後には「ありがとう」と言ってもらえたんです。
大瀬:こちらの想いがちゃんと伝わっているんですね。
伊藤:そう。きっと満足して心と体が一致して、意識が一瞬クリアになったんだと思います。初めは偶然だと思っていたんですが、やればやっただけそうなる。そういうことを繰り返していくうちに、これはただ事じゃないなと。だったら、ちゃんと学ぼうと思うようになりました。
大瀬:すごい!自分に必要なスキルだと!
伊藤:はい。それを学ぶために、2020年に看護師を辞めて、東京から九州へ2人の子どもと一緒にきました。その後モンテッソーリの資格を取り、考え方と生活がさらに変わりました。
前職と今のお仕事の違いや経験を、どう生かしていますか?

大瀬:最初は戸惑いますよね。私は本質で生きるというのはすごく居心地が良くて。一般企業にいたときは、利益も目標も大事なので、時間をかけて人と向き合う時間がとれませんでした。だから目の前にいる子にどれだけ向き合えるか、それは何にも代えがたいものだと感じています。一方で、前社では組織における自分の役割を考えた行動や、マネジメントについても学ぶことができました。PDCAを回しながら営業していた経験は、立場や場所が変わっても自走していくためには必要なスキルだったと感じています。
伊藤:経験したことは全部身になりますね。小児科であらゆる疾患と向き合えたことをはじめ、新人指導、チーム医療をどうまとめるかなどを学べました。
今の会社の社風や働きやすいと感じるのはどんなところですか?

大瀬:上の方々は、そういうスタンスをもっていますね。ただ、それは自分が自立しているかどうかだと思うんです。会社で働く一員としてこの会社で自分に何ができるか、どうありたいかを実現していくために、自ら考えて行動するのはとても大切です。一人ひとりが自立し、お互いの特性を生かしながら協働していく環境が整っているのは、社会的にみても理想的ですよね。
伊藤:まさにそうですよね。一方で、この世界に飛び込んだ直後は、私もそうでしたが戸惑うと思います。園としてのルールや何分待ったらいいですか?という質問が多く聞かれますが、それに答えはないんです。目の前の問題解決ではなく、その行動の本質的な理由にアプローチしなくては何も見えてきません。
大瀬:そうですよね。私にとってはこの職場は、子どもを中心にして、今ここでしかできないことがたくさんある場所だと感じています。実際に義務教育の小学校を義務教育ではない形でつくる、日本では当たり前じゃない学校を選択肢の一つとしてつくろうとしています。自分はどう在りたいか、社会でどんなものをつくっていきたいか、などを日々問いかけながら仕事をしています。
伊藤:私が考えるこの仕事の魅力は、毎日子どもたちから幸せをもらえることです。他人は私の思い通りにはいくわけがないというパラダイムシフトが起きて、この人にとって幸せなことって何だろうと接すると、子どもが自分のことをわかってくれたと満足して、こちらにも心から幸せをくれるんです。それを受けとめられるのがとても幸せです。
大瀬:本当にこの職場は幸せに満ちています。また、どんな個性もひとつの個性であると認められる場所です。子ども一人ひとりが違うように、大人も一人ひとり違います。会社の多様性のなかで、やりたいことや強みを活かして協働できる環境は、“こうあるべき”がないので自由で働きやすいです。